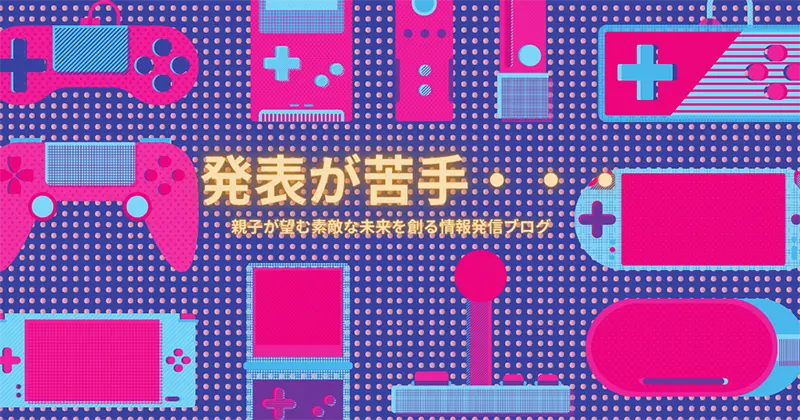「7つの習慣J®」を発達障害の子どもにおすすめする理由6つ
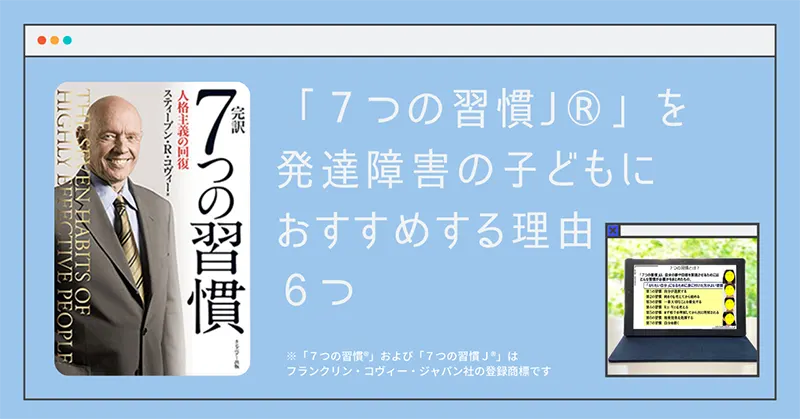
今回は『「7つの習慣J®」を発達障害の子どもにおすすめする理由』6つを紹介します。
諏訪部彩は現在、発達障害の小学生とその保護者の方向けに、日々抱えている悩みや将来への不安を解消して、親子の良好な関係を築き、親子それぞれの素敵な未来を創るサポートをさせて頂いております。
小学生のお子様には、サポートする手段の一つとして、私がファシリテーターの認定を受けている「7つの習慣J®」というプログラムを活用しているのですが、なぜ私が、この「7つの習慣J®」を選び、活用しているのか、子どもにとってどのように良い影響があるのか、について書かせて頂きたいと思います。
- 自信が持てるようになる
- 自己肯定感が高まる
- 将来の目標、夢が持てる
- 自分を大切にし、そして人を大切に出来るようになる
- 自分の特長に気づける
- 自分の選択に責任を持ち、心の自立が出来る
1.自信が持てるようになる
発達障害の子どもが生きづらさを抱える原因の1つとして考えられるのが、「自分に自信が持てないこと」だと考えています。学校など集団生活の場で、落ち着きがなかったり、場違いな言動をしてしまったり、ということを先生や友人からたびたび指摘され「問題児」などとレッテルを貼られてしまう。
本当は人よりも秀でる得意なことや、良い点がたくさんあるのに、「出来ないこと」にフォーカスされて、その一部の面だけで「お前はダメな奴だ」と言われてしまい、自分に自信が持てなくなってしまう。とても勿体ないことだと感じています。「7つの習慣J®」では、自信は人から作ってもらうものではなく、自分で創ることが出来るものだ、と学びます。
こちらの記事で詳しく書いています→「自信」ってなんだろう
「7つの習慣J®」では毎週「自分で決めたことを自分の意思で取り組む」ことにチャレンジしていきます。誰かに言われたからではなく「自分との約束を守る」ことが大事であることを学んでいきます。忘れてしまったり、取り組む気持ちになれない日があったりと、うまくいかないこともあります。それでも、先週より1日でも多く取り組めたらそれは進歩だし、先週よりも少しだけ高い目標を設定出来たら、それも大きな成長です。
誰かとの比較ではありません。過去の自分と比べてどれだけ進歩出来たか、ということにフォーカスしていき、子ども一人一人の成長のペースを大事にして、少しずつかもしれませんが、着実に自信をつけていけるのです。
2.自己肯定感が高まる
自己肯定感が低い、というのも発達障害を持つ人の特徴の1つです。自信が持てない、ということにも関連しています。周囲の人からの評価が低く感じ、叱られたり、否定されることが多いから、良いところも悪いところもひっくるめた「ありのままの自分」を受け入れることが出来ないのですね。「こんな自分は嫌い!」となってしまっているわけです。
「7つの習慣J®」では、ものの見方・考え方、というのは、人それぞれ違うし、同じ物事を見ているとしても、全員が同じことを感じるとは限らない。物事には必ず良い面・悪い面があって表裏一体。そして誰しも長所と短所を持ち合わせていて完璧な人なんていない、捉え方一つで良い方にも悪い方にも変わるのだ。そんなことを学びます。
「7つの習慣J®」を通じた関わりの中で、自分の良い面悪い面含めた特長を知ります。私たちはそれをまるっと受け止め、肯定します。そうしてだんだんと自己肯定感が高まっていくのです。
3.将来の目標、夢が持てる
自己肯定感が低く、自分に自信が持てていないと、なかなか将来の目標や夢、といっても前向きに考えることが出来ない。こんなこともあるかと思います。
「7つの習慣J®」では、上記のように、学びを通じて自分への自信や自己肯定感を高めながら、将来のことについても考える時間があります。目標や夢を持つとともに、そこから逆算して自分がすべきことを考える「終わりを考えてから始める」ということも学びます。
もし、すぐに目標や夢が持てなくても、具体的にならなくても良いのです。まずは、時間を取って考えてみることが大事で「今の時点で自分はまだ将来の目標や夢がはっきりしていないんだ」ということを認識出来るだけでも大きいわけです。決めたら変えてはいけないわけでもありません。途中で変わったっていいのです。自分の将来のことを深く考えていくからこそ、やっぱりこっちかも!という風になるのです。
「終わりを考えてから始める」ことを学んで、これまで頭を抱えていた今の生活態度や勉強に対する姿勢が変わってくる子どもも多いです。
4.自分を大切にし、そして人を大切に出来るようになる
1.のところで、自信をつけるために「自分との約束を守る」ことを大事にする、と書きました。「自分との約束を守る」ということは即ち「自分を大切にしてあげる」ということなのです。
「7つの習慣J®」では、周囲の人と良好な関係を築いていくためには、まずは自分で自分のことを大事に大切にしてあげる、というのが前提の考え方になっています。自分のことを大切に出来ない人が、人のことを大切にすることは出来ないですものね。また、自信がなく、自己肯定感が低いと、自分の意見を主張出来ず我慢して、何事も相手に譲ってしまいがちです。それではなかなか本当の意味で良い人間関係を築くことは難しいのです。
「7つの習慣J®」では「WIN-WIN」の人間関係を目指します。どのようにしてそれを目指すのかも学びます。「WIN-WIN」という言葉自体はよく聞くかもしれませんが、意味を正しく理解している人は意外と少ないのではないでしょうか。「WIN-WIN」の関係を目指すためには、相手の主張を聞き尊重する姿勢は大事なのですが、それと同じく、自分の主張を大事にします。我慢して相手に譲ることはしなくて良いのです。これは自分に自信を持てていて、自己肯定感が高い状態でないと難しいですよね。
だから本当の意味で周囲の人との良好な人間関係を築くためにも「7つの習慣J®」の学びというのはとても大事なのです。
5.自分の特長に気づける
発達障害の子どもは、出来ないことや課題はたくさん指摘されていて、自分でも分かっているけれど、良いところはあまりよく分からない、下手をすると、自分には良いところなんてない!なんて思ってしまっている場合もあるかもしれません。
「7つの習慣J®」で、まずは自分の良いところをたくさん見つけていきます。自分でも探してみるし、周囲の人に聞いてみたり、私から伝えたり。そうすると、自分では良いところだとは思っていなかったけれど、そうだったんだ!と気づくことがたくさん出てきます。そして、ものの見方・考え方を変えてみる、ということを学ぶので、出来ないことや課題も、違う見方をすると良い面に置き換わったり、捉え方を変えることで、前向きに取り組めるようになって課題を克服出来たり、ということも起こります。これも「7つの習慣J®」で学ぶ考え方の習慣ならではだと思います。
そして、誰にでも良いところと悪いところは持ち合わせていて完璧な人は絶対にいない。だから、あなたの良いところを生かして困っている人がいたら助けてあげてほしいし、逆に自分の悪いところ、不得意なところは、どんどん周りの人に助けてもらっていい。そうやって、お互いに良いところを認め合って、そして不得意なところはお互いに助け合って補うことが出来る、そんな考え方を持って、周囲の人と関係を築いていこう、という風に伝えています。
6.自分の選択に責任を持ち、心の自立が出来る
「7つの習慣J®」では、自分の選択で未来の結果が決まる、つまり選択の結果を引き受けるのは自分なのだ、ということを学びます。「自己責任だ」と言われているようで、受け取り方によってはちょっとプレッシャーを感じてしまうかもしれませんが、誰に何を言われようとも、自分のことは自分で選択できる、常に自分の人生の主導権は自分にあるのだ、とポジティブに捉えてもらいたいと考えています。
発達障害の子どもは、もともと主体的な考え方を持っていると、私は感じています。それだけに、得意なことや興味のあることは意欲的にやるけれど、それと逆のことについては、一切やらない、うまくその場をやり過ごすような要領の良さも持たないので、中途半端がないですね。はっきりとしています。
まだ幼い小学生のうちは、この点について保護者の方の関わり方が大事になると考えています。本人の選択の結果、失敗して自信を無くしてしまうことを恐れ、ついつい保護者の方が先回りして、失敗しないようにお膳立てしてしまうこともありますよね。そのようにして選択と結果の法則性をゆがめてしまうと、それは子どものためにならないことが多いです。ですが、あなたがした選択の結果を受け入れることは出来そうか?というのを対話を通じて理解させ、本人がする選択について今一度よく考えてもらうような促しは必要かもしれません。それによって本人にとって良い結果になれば、自分にとって良い選択というのは何なのかを学ぶ機会になっていきます。
そのように、子どもだけではなく「7つの習慣J®」を学ぶ子どもとの関わりを通じて保護者の方にも理解して頂きながら、自信と自己肯定感、主体性を育み、自分の道を自分で切り開いていける、強くてしなやかな心を創っていくのです。
※「7つの習慣®」および「7つの習慣J®」はフランクリン・コヴィー・ジャパン社の登録商標です。