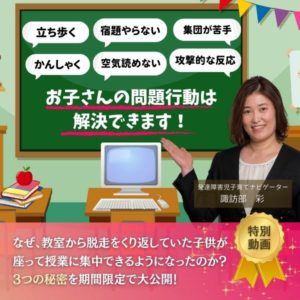発達障害の子がかんしゃくを起こさなくなる効果的な5つの支援策

かんしゃくは「反応」の1つです
感情のコントロールがうまくない、物事へのこだわりが強い、といった特性上、かんしゃくを起こしてしまいやすい子がいます。かんしゃくは「反応」です。
負けたら悔しい、失敗した自分が恥ずかしい、情けない、許せない・・・
そんな出来事や感情が沸き起こった時に、かんしゃくという形で「反応」しています。
つまり、発達障害の子に限らず、誰にでも負けや失敗はあるし、その時に当然ながら悔しかったり、情けなかったり、そういう感情も起きるわけなんです。だから「感情」はOK、そのあとの「反応」をどうするのか。
「反応」をうまく選択することができるように関わってあげましょう。
まずは、あなたの気持ちはよく分かる、私だってそうだから、と理解・共感してあげてください。
自分だけじゃない、誰だってそうなんだ、ということを教えてあげてください。そこがスタートです。
すぐには出来なくても不安に思わず、お子さんのことを決して否定しないで根気よく寄り添ってあげましょう。
学年が上がるにつれ必ず出来るようになっていきますので、安心してください。
かんしゃくを起こさなくなる効果的な支援策
1. かんしゃくを起こした時はいちいち反応せず基本的に無視する
かんしゃくを起こした時はいちいち反応しない、取り合わない、というのが1つです。ようは「無視」する形で、叱ったり、制止したりもしません。ただ、自分を傷つけてしまう行為は危険ですので、その時はそっと黙って抱きしめてあげるなど、安全だけは確保しましょう。
2. かんしゃくが収まったら褒める
かんしゃくが収まったら「よく自分で気持ちを整理出来たね」と褒めてあげます。そっと抱きしめてあげてもいいでしょう。
3. かんしゃくを起こしそうになった時の対処の仕方を教える
かんしゃくを起こしそうになった時、つまり感情が高ぶってカーっとなったらどうするのが良いのか、対処の仕方を一緒に考えてあげてください。例えば、
・その場をいったん離れる
・深呼吸する
・おでこを触る(体のどこでもいいので、スイッチを決めておきます)
4. かんしゃくを起こさずに我慢出来たら褒める
かんしゃくを起こしそうな場面で、しっかり我慢し収めることが出来たら、褒めてあげます。
5. 親が自ら手本を示す
どうやってその感情を収めるか、どういう振る舞いをすることが適切なのか、親が自ら手本を示し、教えてあげてください。そうやって対処方法を学び、親の振舞いを見ながら、かんしゃくという「反応」じゃない、別の「反応」を選択できるように促していきましょう。