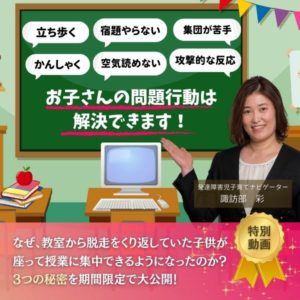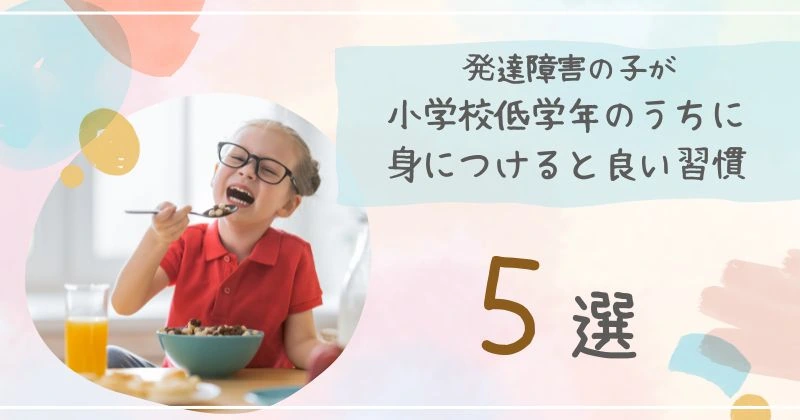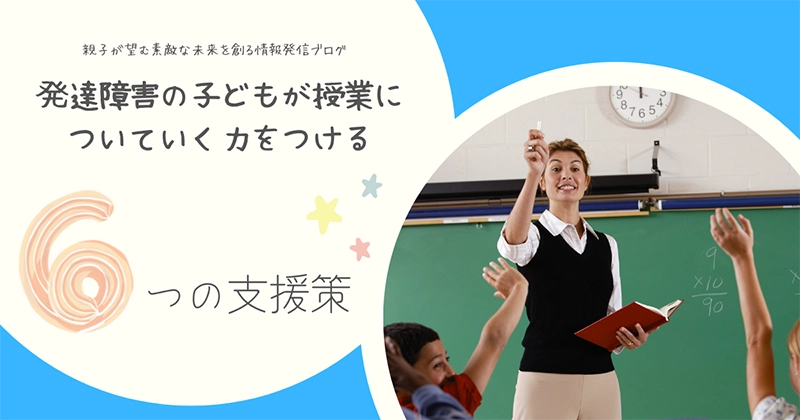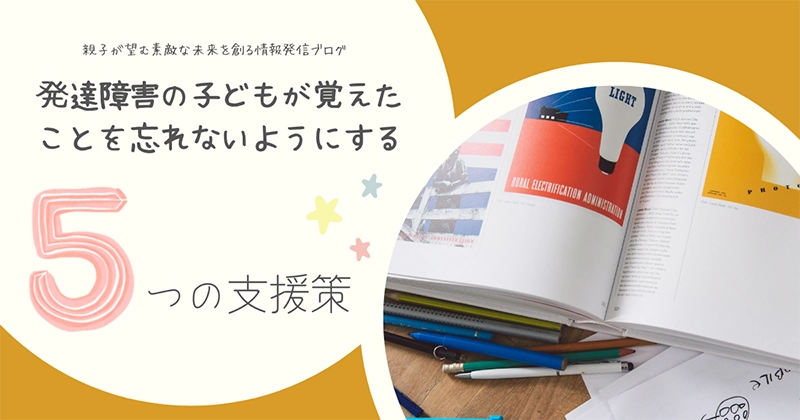発達障害の子どもが指示を理解して動けるようになるための7つの支援ポイント
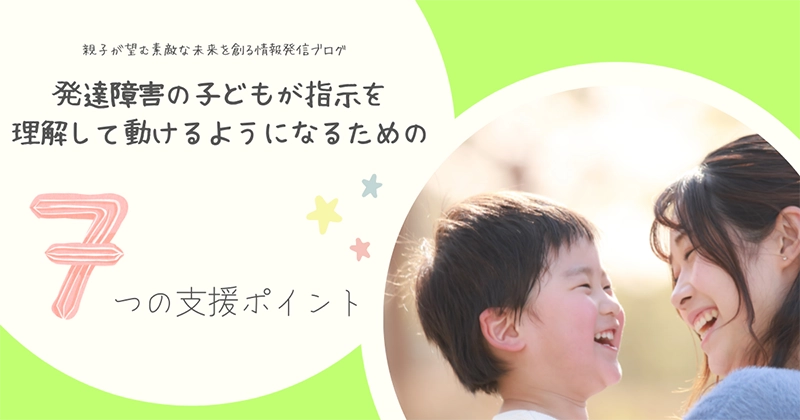
こちらが望む行動が出来ないのには必ず何かしら理由がある
発達障害の子は、特性上様々な理由で、先生や親の指示通りにすんなりと行動出来ない(あるいはしない)ことがあります。
✅指示の内容自体が理解できていない場合
✅やるべきことは分かったけれどやり方が分からない場合
✅やるべきこともやり方も分かるけれどやりたくない場合
と大きくは3つほどのケースが考えられますが、まずは、その子が今どのケースに当てはまっているのかを理解する必要があります。
それをしようとせずに、問答無用でやらせようとするのはNGです。
指示が理解できていない、どうやったら良いかが分からない場合は、その子に伝わりやすい方法で手取り足取り教えてあげれば、頑張って取り組みますし、それで完遂することが出来ればどんどん自信になっていきます。つまり取り掛かれるきっかけのところをしっかりサポートしてあげれば良いわけなんです。
ところが、やりたくないと考えている場合があります。
指示も理解している、やり方も分かっている。けれど、今はやらないと自分で行動を選択しています。
やらないと選択した本人なりの理由が必ずありますので、どのような理由だとしても、まずは聞いて理解を示してあげることが大切です。
『自分の気持ちを理解してくれた』という心の充足感が、次はやってみようという意欲につながります。
ただ、意欲がわくまでの時間はその子それぞれです。こちらからすると長すぎるくらいのタイムラグがあるかもしれません。
場面にもよりますが、出来る限り無理強いをしないで待ってあげる、長い目でその子の成長を見守ろうという姿勢がとても大事です。
7つの支援ポイント
- 指示に従えなくても頭ごなしに怒ったり、理由を聞かないまま無理やり従わせたりしない
- 指示に従うことが出来ない理由を探ってみる
- 指示内容が理解できていなければ口頭だけでなく文章や図で書いて示してあげるなどの伝える工夫をする
- 指示は理解しているけれどやり方が分からない場合は、手本を示したり、指示を小分けにしたりしてスモールステップを踏ませてみる
- やり方は分かっているけれどやろうとしない場合は、やらない理由や気持ちを聞いてあげ、けっして否定せずに理解を示す
- なぜそれをする必要があるのか、目的や意図を説明してあげ、納得したうえで取り組めるようにしてあげる
- それでも取り組めない時は無理強いせず、少し時間を置く、機会を改めるなどして、出来るだけ待ってあげる余裕を大人である我々が持つ